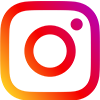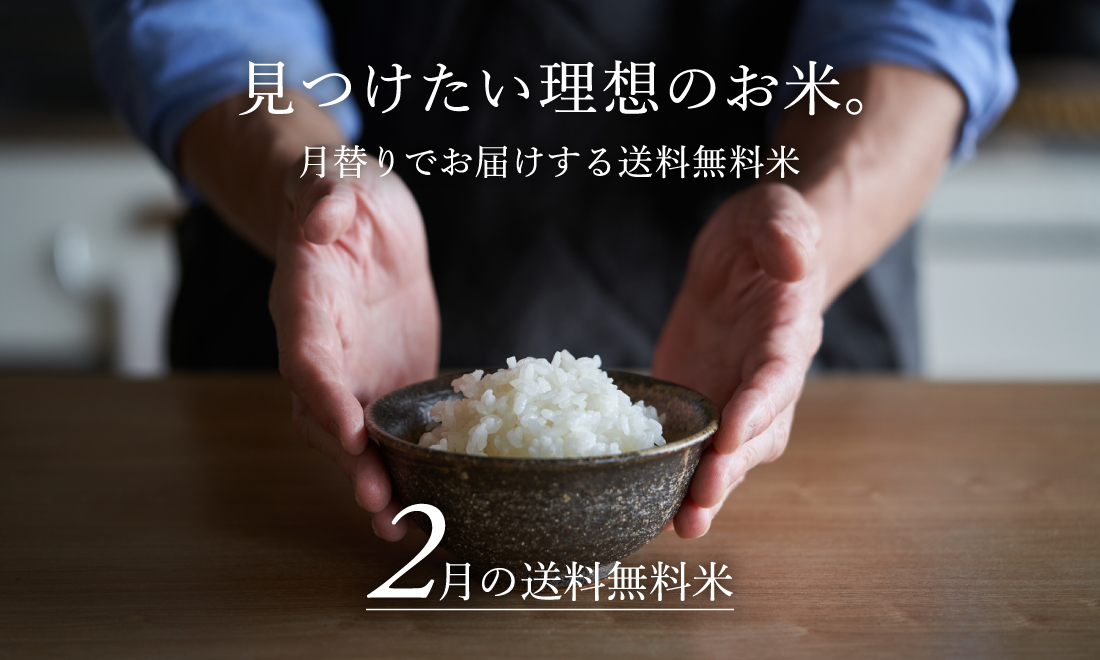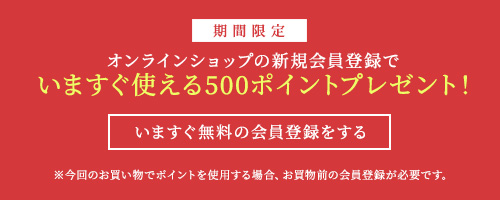1年に1度、ころんと愛らしい梅の実が店先に並ぶ季節。
梅干しをはじめとする、旬の食材を使った手作りの保存食は、先人の知恵が詰まった日本の伝統です。
今年こそ、自分も“梅しごと”をしたい!と思っている方にも作りやすい、梅干しの作り方をご紹介します。
また、単なる保存食といった意味合いだけでなく、伝統的な製法で作られた梅干しには、身体にうれしい効能もたくさん。
梅干しのクエン酸には、殺菌作用や、疲労回復や消化を助け、カルシウムや鉄分などのミネラルの吸収を促す作用などがあります。
「梅はその日の難逃れ」という、昔からあることわざがあります。梅干しを朝食べれば、その日一日災難から逃れることができる、という意味です。
1年間の健康を願って、梅干しを作ってみませんか?
昔ながらの梅干しは塩分20%以上のものも多いですが、少し塩を控えた塩分15%の少しマイルドな梅干しの作り方をご紹介します。
シンプルな材料で、自家製赤しそ梅干し
【赤しそ梅干し(塩分15%)】作り方



準備するもの
- 保存容器
- 漬けたい梅の2~3倍の容量のもの
(酸や塩分に強いガラスやホーロー、陶器など。金属は錆びやすいため避けましょう。)
- 消毒用のホワイトリカーや焼酎
- アルコール35%以上
- 竹串
- 重石
- ビニール袋に塩や砂糖1kg~を入れ、重石として使用できます。
- 干す用の竹ザルなど
- しその色がつくので、汚れても良いもの。クッキングシートを敷いても
材料(梅1kg分)
〈塩漬け用〉
- 完熟梅
- 1kg ※青みの残る梅は、数日置いて追熟させる
- 塩(梅用)
- 150g(梅の15%) ※自然塩・天然塩など
〈追加用〉
- 赤しそ
- 約200g(※梅より後に購入し、新鮮なものを漬ける
- 塩(赤しそ用)
- 30g
作り方
【下準備】
❶ 保存容器を消毒する。アルコール度数の高い(35度以上)焼酎やホワイトリカーなどを、霧吹きなどで吹き付けるか、キッチンペーパーに含ませて丁寧に拭く。鍋に入るサイズであれば、煮沸消毒してしっかり乾かしてもOK。

❷ 梅は、ひとつひとつ確認し、傷のあるもの、傷んでいるものを除いてきれいなものを選別する。

※傷のある梅は、傷んだ部分を切り落とし、保存容器に入れてしょう油漬けにすれば、手軽でおいしい梅風味の万能調味料に!
梅の下漬け
❶ 梅は傷つけないよう、やさしく洗う。ザルにあげて水気をきり、清潔なふきんやキッチンペーパーで丁寧に水気を拭く。

❷ 梅を傷つけないよう丁寧に、竹串でへたを取る。

❸ 保存容器の底に、塩を薄く均等に広げ、梅を並べ入れる。

❹ 同様に、塩を振り入れ、梅を並べ入れる作業を交互に行う。上のほうが塩が多くなるよう、調整しながら入れると良い。

❺ 最後は表面を覆うように塩を入れ、重石をのせる。蓋が閉まるようであれば閉め、冷暗所で保存する。

❻ 翌日くらいから梅酢が上がりはじめる。梅酢があまり上がってこなければ、重石を増やす。5日から1週間ほどで、全体がたっぷりと浸る。

【本漬け(赤しそ漬け)】
※梅を漬けて1週間~10日後くらいが目安
❶ 赤しそは、葉のみを摘み取る。お好みで、軸も除く。たっぷりの水で洗い、水気をきる。

❷ ボウル(ガラスやほうろう)に赤しその葉と塩の半量を入れ、手でしっかりともみ込む。

❸ アクを含んだ黒っぽい汁が出てきたら、ぎゅっと絞って捨てる。

❹ 残りの塩を加えて同様に繰り返し、アクをしっかりと出す。

❺ 梅酢を大さじ2程度加えると、鮮やかな赤紫色に変わる。


❻ 梅の上に、赤しそをほぐしながら加え、汁も回し入れる。

❼ 重石を戻し入れ、全体が梅酢に浸かるようにした状態で、土用干しまで冷暗所で保存する。

【土用干し】
※梅雨が明け、3日ほど晴天が続くタイミングで干す。
※梅のサイズによって干す時間を調整しても。【目安】小梅→2日、大きい梅(3Lなど)→4日程度
❶ 竹ザルに、汁気をきった梅と、汁気をしっかり絞った赤しそを広げる。日光がよくあたる場所に干す。梅酢の瓶も、1日は一緒に日光に当てる。



❷ 夜は室内に取り入れ、翌朝、上下を返してから天日に当てて干す。約3日間繰り返す。


❸ 梅干しを保存する容器は、消毒して清潔にしておく。

❹ 干し終わった梅を保存容器に移す。
・かためが好みならそのまま保存容器へ。
・一度梅酢にくぐらせてから保存すれば、少しふっくら。
・梅酢に浸るように保存すれば、やわらかくジューシーな梅干しに。


❺ 完成!すぐに食べることもできるが、時間が経つと角が取れて、まろやかな味わいへと変化する。

ここがポイント!!
シンプルな材料ゆえ、素材選びがとても大切です。梅はもちろん、使う塩も天然のミネラル豊富なおいしい塩を使用するのがおすすめです。
はじめてでも失敗しないコツは、
・道具はきちんと消毒しておく。
・作業する手はしっかり洗う。手袋などを着用しても。
・中玉サイズの梅を選び、傷んだ梅は取り除いておく。
・梅酢から梅が出ないように気をつける。
です。保存中にカビなどのトラブルがおこらないよう、丁寧に作業しましょう。
赤しそを加えずに、同じ方法で作ることもできます。
白干し梅と呼ばれ、違った味わいが楽しめますので、食べ比べてみるのもおすすめです♪