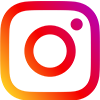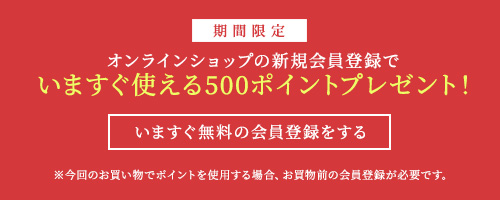皆さんはカレーが好きですか?
学校給食の人気メニューでもいつもランクインするように、日本人はカレーが大好き。
日本でカレーがこんなにも定着したのは、カレーがごはんとドッキングした“米飯料理”であることが関係しています。
海を超えて瑞穂の国日本に伝わり、独自の変容を遂げた、日本のカレー。
その変遷や、意外と知らないカレーの小話などをご紹介します♪
目次

カレーの日とは。日付や由来
「カレーの日(カレーライスの日)」は、カレーの普及を目的として、全日本カレー工業協同組合によって制定された記念日です。
毎年1月22日が「カレーの日」とされています。
なぜ1月22日なのかというと、昭和57年(1982年)、社団法人全国学校栄養士協議会が、全国一斉で1月22日にカレー給食の提供を呼び掛けたことに由来しています。
当時、このカレー給食の取り組みは新聞各社にも取り上げられました。
朝日新聞の夕刊では、
【カレー給食 賛否の中 いただきまーす 三百市町村は見送り 文部省も援護メニュー】
という見出しで、社会的にも関心が寄せられたカレー給食の日について、記事が出ています。
昭和58年に全国の小学校90校で行われた「学校給食でのメイン料理の出現回数頻度」においても、カレーライスは1位。当時からカレーが子どもたちから絶大な人気を誇っていたことがうかがえます。
参考:全日本カレー工業協同組合 1月22日はカレーの日https://www.curry.or.jp/currysday/
参考文献:小菅 桂子「カレーライスの誕生」株式会社講談社2002年6月 p208-210 カレーの現代 カレー記念日
実はたくさんある、カレーの記念日
「カレーの日(カレーライスの日)」以外にも、カレーにまつわる記念日があります。
2月12日 「ボンカレーの日」「レトルトカレーの日」
…大塚食品株式会社が制定。1968年2月12日に、世界初の市販用レトルトカレー「ボンカレー」を発売したことが由来。
3月2日 「ご当地レトルトカレーの日」
…一般社団法人ご当地レトルトカレー協会が制定。カレーの日(1月22日)、レトルトカレーの日(2月12日)の並びに続く形で、3月2日を地域の活性化を目的としたご当地レトルトカレーの日とした。
6月2日 「カレー記念日」
…横浜カレーミュージアムが制定。1859年の6月2日に横浜港が開港し、その後カレーが日本に伝わったことに由来。
6月12日 「恋と革命のインドカリーの日」
…新宿中村屋が制定。 1927(昭和 2)年 6 月 12 日に、同社が日本で初めて本場インドの「純印度式
カリー」を発売したことが由来。
8月2日 「カレーうどんの日」
…カレーうどん100年革新プロジェクトが制定。カレーの日(6月2日)、うどんの日(7月2日)の並びに続く形で、8月2日を食全体における「カレーうどん」の地位向上のためカレーうどんの日とした。
12月1日 「カレー南蛮の日)」
…カレーうどんの日と同じく、カレーうどん100年革新プロジェクトが制定。カレーうどんを日本全国に広めたとされる中目黒「朝松庵」の2代目店主の誕生日が12月1日だったことが由来。
参考:ボンカレー HP
参考:日本食糧新聞 電子版
参考:新宿中村屋
参考:カレーうどん100年革新プロジェクト プレスリリース ついに「カレーうどんの日」が8月2日に決定!
参考:カレーうどん100年革新プロジェクト プレスリリース 12月1日(水)「カレー南蛮の日」を制定!
インドに「カレー」という料理はない!?カレーの語源

カレー発祥の国、インドでは、日本人が思い浮かべるようなカレーライスは、実はありません。
日本のカレーライスを食べたインド人が、「これは何の料理ですか?」と尋ねたという話もあるほど。
インドでは、様々なスパイスを組み合わせた料理が、日本の定食のように、お米やナン、チャパティなどの主食と、副菜を数種類組み合わされて食べられることが多いです。定食のようなスタイルは、ミールスや、ターリーと呼ばれています。
カレーの語源は、
南インドのタミル語で「ソース」や「煮込み」といった意味のある「カリ(Kari)」という言葉からという説や、
ヒンズー語で「美味しいもの」といった意味のある「ターカリー(Turcarri)」からきている説などがあります。
カレーの故郷インドではなく、イギリスなどに伝わった後、スパイスを使った料理の英語名としてカレー(Curry)が使われるようになったといわれています。
イギリスで進化した欧風カレー
日本でカレーライスといえば思い浮かぶ、とろりと濃度のある、カレールーを使ったカレーライスの原型は、インドではなくイギリスから伝わったものです。
1772年頃、英国の東インド社のウォーレン・ヘイスティングズが、イギリスにカレーの原料とお米を持ち帰ったことで、イギリスにカレーが広まりました。
ヴィクトリア女王もカレーを食べていたそうで、イギリスの上流階級の中でもカレーは人気があったようです。
インドではカレーとパン(ナンやチャパティ)の組み合わせも多いのですが、
当初イギリスが植民地としていたインドのベンガル地方ではお米が主食だったため、「ご飯×カレー」のスタイルが、イギリスに伝わったとされています。
西洋料理には、ビーフシチューなどのように、小麦粉を使って煮汁に濃度をつける、という調理法があります。
そこから、カレーにも小麦粉を加え、とろりと濃度をつける作り方が生まれました。
日本の「カレーライス」が生まれるまで。日本のカレーの歴史
日本とカレーは、西洋料理として出会います。
1872年の料理書「西洋料理指南」で、初めて日本にカレーの調理法が紹介されました。
そのレシピには、
“ねぎと生姜とニンニクのみじん切りをバターで炒めて水を加え、エビやカキ、カエルなどを入れて煮、カレー粉を加えて1時間ほど煮る。塩で味を調え、水溶き小麦粉でとろみをつける。”
とあります。(カエルが登場するのはびっくりですね。)
インドカレーにはない、小麦粉を使って濃度をつける、というポイントが、現在にも受け継がれるカレーライスのルーに共通しています。
その後、1876年にはクラーク博士が、札幌農学校の生徒に、栄養食としてライスカレーを奨励したそうです。
18世紀末にイギリスのC&B社がスパイスを調合し、“カレー粉”が発売されると、日本にも輸入されるようになります。
1923年、ヱスビー食品の創業者である山崎峯次郎が、日本初の国産カレー粉を発売します。山崎氏は東京でカレーを食べて感激したことをきっかけに、当時情報のない中努力を重ね、カレー粉の開発に至ったそうです。
1930年には、家庭向けにカレー粉が発売され、広がりを見せたものの、1941年の戦争の勃発により、家庭用のカレー粉の製造は中止を余儀なくされました。(軍用食品としてのカレー粉の製造は続けられていました。)
当時、カレーライスは、「辛味入汁掛飯」と呼ばれていたそうです。
1954年、日本初の固形即席カレー(カレールー)が登場します。
スパイスを調合したカレー粉に、油脂やうま味をプラスする調味料、小麦粉などがあらかじめ混ざっているため、誰でも手軽にカレーが作れるとして定番化しました。
参考文献:旭屋出版MOOK「カレー大全」株式会社旭屋出版 平成21年8月
カレー具材の定番が、じゃがいも、玉ねぎ、人参なのはなぜ?

今の日本では、カレーライスの定番具材といえば、
・じゃがいも
・玉ねぎ
・人参
のイメージではないでしょうか。
しかし、カレーライスの三種の神器ともいえる3つの野菜がカレーの具材として定着したのは、明治時代以降です。
どれも海外から日本に伝わってきた野菜です。
・じゃがいも…早くから日本に伝わっていたものの、最初は日本人の口に合わず、家畜のエサとしてや、飢饉の際の非常食として作られていました。寒冷地のほうが栽培しやすいため、北海道や東北、北陸地方で作られ、お米のあまり育たない地域では主食としても用いられていました。
・玉ねぎ…江戸時代には長崎に伝わり、明治以降北海道での栽培が盛んになったといわれています。明治25年にコレラが流行したことで、伝染病に効くとの噂から、玉ねぎが広がります。カレーライスは最初、玉ねぎではなくネギを使った料理として紹介されていますが、玉ねぎの普及とともに徐々に入れ替わっていきます。
・人参…16世紀に中国から伝わり、当時のアジア系の人参は、香りの強い朝鮮人参(高麗人参)のような長い人参でした。後に、オレンジ色でやや太い西洋人参が入ってきてからが、こちらが多くなります。
日本でのじゃがいも、玉ねぎ、人参の定着とともに、明治時代の終わりごろにはこれらがカレーに集合します。
明治44年の「洋食の調理」や、大正4年の「家庭実用献立と料理法」などでは、カレーの材料としてこれら3つが勢ぞろいしています。
日本ならではの、じゃがいも、人参、玉ねぎを具材として加えるカレーが定番化したのには、日本人が料理を「目でも楽しむ」ことが関係しているのではないかという考察も。
ターメリックを基調とした黄色一色のルーだけではなく、クリーム色がかったじゃがいも、鮮やかなオレンジ色の人参、透き通った玉ねぎが映えるルーに、白いご飯のコントラスト。添えられた福神漬けが赤く色付けされ、彩りが意識されていることにも、日本らしさを感じます。
一口大のごろっとした大きさで具材感を出し、食べ進めるうちに食感や味わいの違いを楽しめることも、カレーが日本人を魅了している理由の一つなのかもしれませんね。
関西では牛肉カレー、関東では豚肉カレーが定番説
あなたがカレーを作るとき、材料としてぱっと思い浮かぶのは牛肉でしょうか、豚肉でしょうか。(鶏肉や魚介類かもしれませんね。)
カレーに限らず、肉じゃがや肉豆腐など、「肉といえば?」と問われると、関西と関東で答えが違うというのは有名です。中華まんじゅうを「肉まん」と呼ぶか、「豚まん」と呼ぶかなども同じ議論ですね。
ハウス食品が7,663人に調査した2020年度版「日本全国カレー白書」の結果をみても、
関西は牛肉、関東は豚肉が人気であるという結果が出ています。
関西では牛肉、関東では豚肉が人気の理由は何なのでしょうか。
そもそも、関西と関東では、牛肉と豚肉の消費量が違います。
歴史を辿ると、日本人の肉食文化は、明治の文明開化後の牛鍋ブームにより、東西ともに牛肉からスタートしています。
しかしその後、日清、日露戦争の影響で缶詰に加工された牛肉が軍需食料として送られるようになると、牛肉の価格が暴騰します。
その流れで豚肉が注目されるようになり、生産量も増加します。
明治の終わりごろには豚肉料理に関する記事やレシピも一般家庭に出回るようになり、以降関東では豚肉が定着し、消費量も多くなっています。
対して関西では、もともと農耕用の家畜として、馬ではなく牛が主流でした。そのため、もともと牛との関係が深く、身近なものであったという背景があります。
肉食文化を持ち込んだ外国人からも、但馬牛など兵庫の牛肉が高く評価されるなど、関西にブランド牛の産地が多いことにもつながっています。
関西では牛肉の消費量が豚肉よりも多い時代が続きました。
しかし、最近は食品の価格高騰などの影響もあり、関西での牛肉への支出額に変化がみられています。
総務省の家計調査では、2023年には近畿地方の牛肉支出額は、遂に豚肉の支出額と並んだとあります。
節約志向により、他と比べてより高価格帯である牛肉を買い控える家庭も増えているようです。
時代の変化と共に、関西でカレーと言えば牛肉説も、徐々に崩れていくのかもしれません。
また、九州地方ではもともと鶏肉文化が強いこともあり、カレーの肉といえば、「鶏肉」がトップ。
北海道では、なんと「魚介類」がトップという結果も!
多様な食文化をもつ日本らしく、カレーライスにも地域によって、家庭によって、豊かな特色があるようです。
参考:ハウス食品 地域によってこんなに違う!2020年度版「日本全国カレー白書」
参考:日本経済新聞 近畿「牛肉1強」に異変? 支出額、豚肉が並ぶ 2024年4月14日
参考文献:小菅 桂子「カレーライスの誕生」株式会社講談社2002年6月
日本人がカレー好きな理由は「米」「ごはん」にあり。
日本で、カレーがこれほどまでに人気になったのは、日本人がお米を主食とする民族であるということが一番の理由のようです。
西洋文化が日本に入ってきたころ、洋食になじみのない人でも、慣れ親しんだごはんが添えられた「カレーライス」には、とっつきやすかったのでしょう。
ごはんと一緒に味わうスタイルが、日本人のライフスタイルと味覚にマッチしたのですね。
カレーは、大量調理のしやすさからも、日本人の食事に重宝されました。軍隊や、農村で大勢の食事を用意する機会にも、お米との相性が良く、今でも学校での調理実習や、野外活動のメニューの定番となっています。
カレーに合うお米の選び方、炊き方

カレーライスには、とろりと水分のあるルーをごはんにかけるといった特徴をふまえ、お米を選びましょう。
ぱらりと仕上がりやすい、玄米や発芽玄米、雑穀米などもおすすめです。
炊き方にもコツがあります。
カレーの汁気を適度にまとい、口にしたときのバランスが良くなるよう、少し固めに、水分量を控えてぱらりと炊き上げるのがおすすめです。
酢飯用に炊くお米のように、加える水の量を1割ほど減らしてみましょう。
水分を減らして炊く場合は、炊き上がった後の蒸らしの工程をしっかり取ることで、芯が残りにくく、食感よく仕上がります。
また、裏技として、米油少々(入れすぎ注意)を加えて炊くと、米粒どうしの離れがよく、油脂を含んだルーとの絡みも良くなります。
また、ターメリックやサフランなどのスパイスを加えて炊くのもおすすめ。
野菜カレーなどあっさりとしたカレーには、スパイスやレーズン、バター入りのごはんなどで、ライスのほうにも味のアクセントをつけると、満足感がぐっとアップします。
参考文献:旭屋出版MOOK「カレー大全」株式会社旭屋出版 平成21年8月
カレーにおすすめのお米

【白米・玄米】ヤマチョウ(佐々木大作)さんの
秋田県にかほ市産ササニシキ(自然栽培米)
心から安心して食べられるものを届けることを第一に考え、全て自然栽培で米作りをしています。冷めても美味しいササニシキをぜひご賞味ください。

【白米・玄米】加賀米野菜基地さんの
石川県金沢市産いのちの壱(有機栽培米)
美味しさと、大粒の存在感、キラキラつやつやとした見た目の良さから幻のお米と呼ばれることも多い品種です。栽培期間中、農薬と化学肥料を一切使わずに育てました。

萱森農園(萱森教之)さんの
新潟県加茂市産「発芽玄米」(600g)
新潟産植酸栽培コシヒカリと新潟産うるち米のブレンド玄米を自社工場で発芽させました。ふっくらプチプチ食感をお楽しみください。発芽玄米はとても栄養価が高く、一般的に糖質の吸収バランスを調整してくれると言われています。
名脇役、福神漬けのストーリー

日本的カレーライスといえば、欠かせないのが福神漬け!カレーライスの薬味の定番として不動の地位を築いている福神漬けは、いつカレーと出会ったのでしょうか。
まず、福神漬けとは、大根、なす、瓜、きゅうり、生姜、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけなどの材料から5種類以上を、しょう油とみりんなどで漬けたものです。
名前の由来は「七福神」だとか。
当初7種類の具材を使っていたことから発想を得て、縁起の良い名前がつけられたという説があります。
カレー×福神漬けのコンビが最初に生まれたのは、諸説ありますが、明治35年頃、日本郵船のヨーロッパ航路の一等客室で出していたチャツネがなくなり、福神漬けで代用した説が有力です。
二等以降の客室では、たくあんを添えていたという資料が残っているのも面白いです。
牛丼には紅しょうが、とんかつにはごはんとお味噌汁がセットで定着したように、国民食として受け入れられたカレーライスには、日本のお漬物、福神漬けの存在はなくてはならないものであったのかもしれません。
福神漬けの永遠のライバルには、日本版ピクルス・らっきょうという存在もありますが…!
参考文献:小菅 桂子「カレーライスの誕生」株式会社講談社2002年6月
参考文献:よこたとくお 「まんがで学習 おもしろカレーライス物語」 株式会社あかね書房 1993年7月
カレーの日の献立と、スパイスカレーレシピ

カレーライスの日、カレーの他に何を用意すれば良い…?と献立やおかずに悩まれる方も多いようです。
人気なのは、
・サラダ(野菜サラダ、マカロニサラダ、ポテトサラダ、ピクルス類など)
・スープ類
・揚げ物(とんかつ、唐揚げ、コロッケ、フライなど)
などのようです。
カレーは、1品でも主食(炭水化物)、主菜(たんぱく質)、副菜(野菜)の要素がカバーできます。
カレーの日は、具沢山のカレールーにして、1品だけで十分!と気楽に構えるのも◎
最近は、インドカレーやスリランカカレー、タイのグリーンカレーなど、海外のカレー人気などもあり、副菜を色々用意するスタイルも人気です。
ルーを使わない、スパイスカレーのレシピは以下の記事を参考にしてみてくださいね。
気軽に作れる副菜の作り方もご紹介しています。
→関連記事【グルテンフリー・ヴィーガン】 オクラとひよこ豆の玄米スパイスカレー
おすすめのお米

しつはらふぁーむさんの
石川県七尾市産プリンセスサリー(自然栽培米)
インドの高級米「バスマティライス」と日本の米を掛け合わせたお米です。特有の香ばしい香りと、ぱらりとした食感を楽しむことができます。カレーやスパイス料理にピッタリです。